汎兮堂箚記 #8 『室町の覇者 足利義満 ― 朝廷と幕府はいかに統一されたか』(桃崎有一郎)
書名
『室町の覇者 足利義満 ― 朝廷と幕府はいかに統一されたか』
著者
桃崎有一郎
刊行
発行:筑摩書房 2020年1月
メモ
タイトルのとおり、本書の主役は足利義満ですが、実際に描かれているのは室町幕府の成立前史から足利義教(第6代将軍)の時代までの長きにわたっています。「室町殿」そして「北山殿」という中世権力の最高峰に到達した義満が、なぜそのような権力を希求することになったのかを説明するためには室町幕府の成立過程と観応の擾乱について触れざるを得ないためであり、また、その権力が何を達成し、どんな問題を残したのかを理解するためには、彼の後継者たちがどのように権力を受け継いでいったかを見ていく必要があるからです。著者は、近年の研究成果と自身による新たな発見をもとにして、上記の問題を解き明かしていきます。
実際のところ、読み始めても義満以前の話が延々続くため、いつになったら義満が出てくるんだ、という気になるかもしれませんが、ここの部分が本書全体の基礎となる部分なので、ぜひ飛ばさずに読んでいただきたいと思います。
以下、思いつくままに備忘録
- 足利幕府の実体は直義と彼に従う足利一門の大名たちが作った。彼らはそもそも鎌倉幕府を滅ぼしたとは思っておらず、北条氏を滅ぼしただけという意識。北条氏の執権のかわりに直義が実権を握って幕府を実質的に再起動し、そこに尊氏がトップとして迎えるかたちで足利幕府は始まった。尊氏が鎌倉幕府の宮将軍のように完全なお飾りであれば、直義による「執権政治」がスムーズに構築されたはずだが、実際には尊氏は直義の兄であり、足利氏の惣領だから、御家人たちと全くつながりのない宮将軍のようにはいかない。尊氏自身はすべてを直義に任せるつもりでいたが、高師直ら尊氏の周囲がそれを許さず、直義は失脚する。自分たちこそが足利幕府を作ったと自負する直義と彼に従う大名たちは政権を奪還すべく南朝と手を結んで決起し、観応の擾乱が始まる。
- 観応の擾乱は直義の敗北で終わるが、直義派の有力大名たちは健在で、南朝に味方して幕府に反抗しつづけた。彼らは自力で領国を実効支配していて、幕府に頼る必要はない。結局、幕府は彼らの既得権益を追認することで幕府に取り込むしか方法がなかった。大名たちはいったん幕府に帰順しても、気に入らないことがあれば、いつでも南朝をかついで反抗できる。直義は敗北したが、直義派は既得権を保持したまま幕府に戻り、幕府の中枢を握った。
- こういう状況のなか将軍になった義満は、問題の本質を見抜き、それを解決するために達成すべきことの優先順位を定めた。有力大名たちが幕府に反抗する際、南朝の権威を利用する。これを防ぐためには南北朝を統一して南朝を消滅させるしかない。ところが、南朝は幕府との対等の交渉には応じない。幕府の長は将軍であり、形式上、将軍は天皇の臣下にすぎないからだ。そこで義満は北朝を支配してその代表者となり、北朝の代表者として南朝と交渉するという方法を考えついた。そのためにあらゆる手段を使って廷臣たちを支配下に置いていく。先例も慣習も超越した存在となり、摂関も天皇も治天も誰もその意向には逆らえない。こうして北朝支配を完成させ、北朝の代表を兼ねる幕府の長「室町殿」となった義満は、有力大名の内紛を扇動・利用して弱体化させることにも成功し、彼らが南朝と結んで幕府に対抗する可能性の芽を摘んで南朝を孤立させた。追い詰められた南朝は、北朝代表の義満との講和に応じ、南北朝の合一が成った。
- 太政大臣になったあと出家した義満は、君主でも臣下でもない存在として朝廷と幕府を外から支配する超越的支配者「北山殿」になった。義満は妻の康子を後小松天皇の准母(母代わり)にし、息子の義嗣を後小松天皇の猶子(養育関係にない義理の息子)にした。義満自身への太上天皇尊号宣下の手続きを行わせようと動いていたことも明らかになっているし、義嗣への親王宣下も予定されていた。しかし、義満は自身の構想を誰とも共有していなかったので、その後の朝廷・幕府についての構想の中身は義満の死によって永遠に不明になった。後小松天皇の実子が成長するまでのつなぎとして「義嗣親王」が天皇に即位、あるいは「義嗣親王」が将軍になることで「足利氏の親王将軍」を実現、などが推測される。
- 4代将軍義持は父・義満への反発から、義満のやったことをすべて否定した、というイメージが普及しているが、実際は取捨選択して受け継ぐべきは受け継いでいる。義満のような露骨な廷臣支配は控え、権力の行使も抑制的だったが、朝廷への関与は続けている。義満のように直接朝廷を支配するというより、後見役、チェック役として必要な場合に口を出すという形だが、最終的には後小松上皇が院宣を出す際には義持が必ず事前にチェックするというルールを確立した。義満が力ずくのなりふりかまわぬ強権で実現した朝廷支配を、義持はそのような強権を用いず、官職にも依存せずに実現したことから、現在では、義持のほうが権力として完成されているという指摘もある。

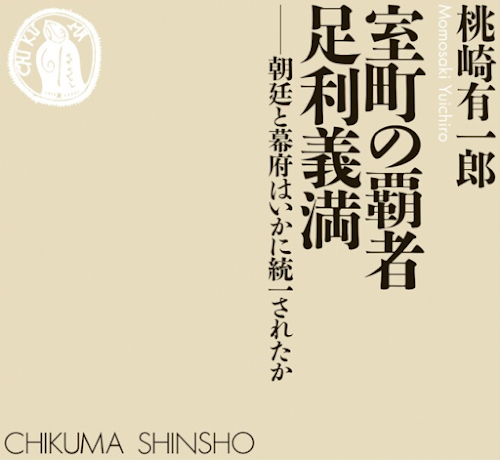
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cf971c0.05a4960b.3cf971c1.a3fe3a12/?me_id=1213310&item_id=19865993&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2795%2F9784480072795_1_130.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿